【発達障害の基礎知識】注意欠如多動症徹底解説
2025年08月06日 13:28
今回は発達障害の中でもADHD(注意欠如多動症)についてまとめていきます。
注意欠如多動症(ADHD)とは
注意欠如多動症(ADHD)は、発達障害(神経発達症)の一つです。
神経発達症は大人になってから困りごとが現れるのではなく、幼少期から継続して特定のスキルの獲得や情報の獲得、保持、応用をすることに困難さを伴うというのが診断の基準となります。
ADHDには3つの型があります。
不注意型
多動・衝動型
混合型
これらの型はありますが、程度は人によりさまざまです。
また、その時に与えられている環境によっても、この特性が強く出やすいのか、自分でコントロールができるのかにも大きく影響があります。
診断基準
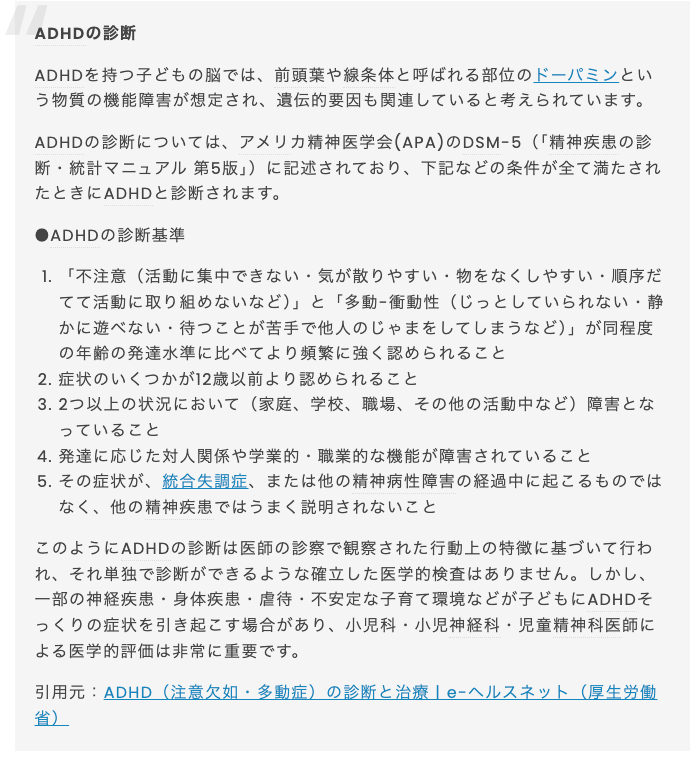 注意欠如多動症かどうかの診断はDSM-5やICD-11などの世界的な診断基準や『注意欠如・多動症‒ADHD‒診断・治療ガイドライン』に基づいて診断をされます。
注意欠如多動症かどうかの診断はDSM-5やICD-11などの世界的な診断基準や『注意欠如・多動症‒ADHD‒診断・治療ガイドライン』に基づいて診断をされます。
診断はDrが行います。
診察ではお子さんの診察のほかに、ご家庭での困りごとや園や学校、集団生活の中での困りごとがあるか、たくさんお話しを聞いた上で診断につながっていきます。
今、お子さんの姿で悩んでいる方は、お子さんの様子を動画に記録したり、具体的なシーンをメモしておき、それをDrに見せながら相談することをおすすめいたします。
幼児期に見られやすい注意欠如多動症(ADHD)の症状
この姿が見られたからといってADHDなわけではありません。
このような姿として、見られることがあるなという様子をまとめるので、イメージを持ってもらえると嬉しいです。
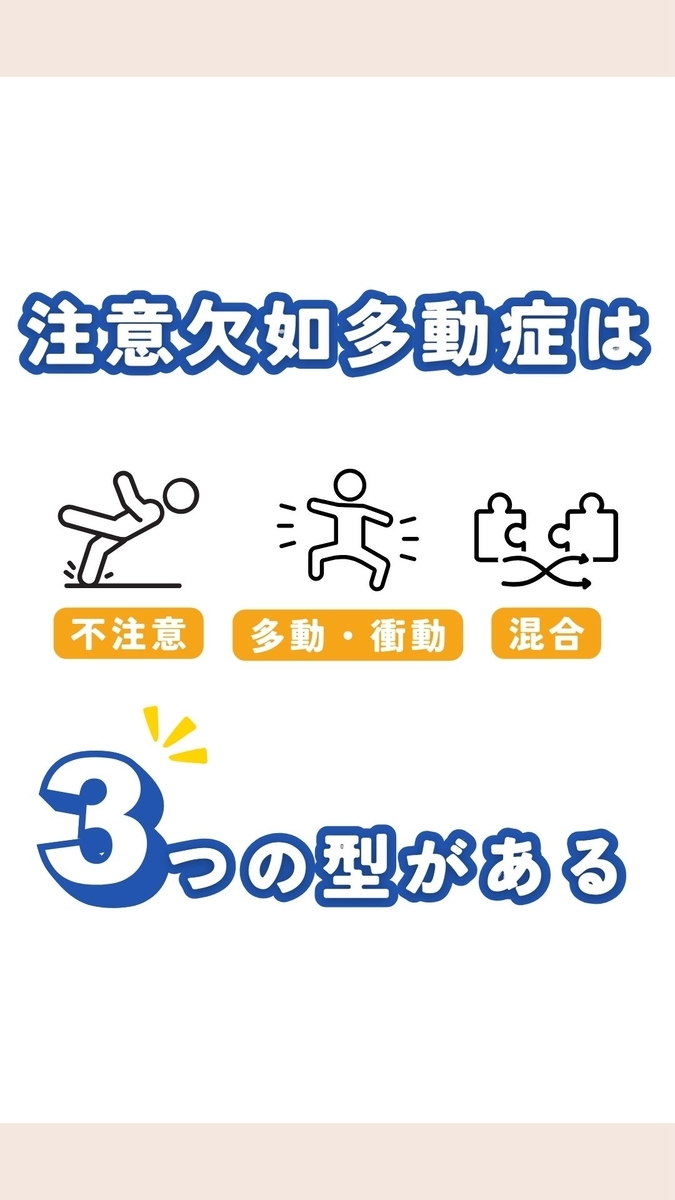
不注意型
いろんなことに興味がある
一緒に遊ぶことが大好き
好奇心が旺盛
困った子と言われるよりは、社交性の高い子とみられることが多いような印象です。
多動性
じっとしていることが苦手
集団でお話を聞くことが苦手
お部屋から飛び出してしまう
とても活発である
多動性は、幼児期の年齢では周りに影響されることも多いにあります。
ですので、年齢なのか特性なのか、判断が難しいところでもあります。
衝動性
繋いでいる手を振り払う
突然飛び出す
順番が待てない
おもちゃを取り上げる
周りの子を押す、叩くなど
幼児期に衝動性が強いお子さんは「困った子」として注目されることが多い印象です。
また、衝動性が強いお子さんは癇癪が激しかったり、売り言葉に買い言葉というように大人をイラつかせやすいかもしれません。
特に「乱暴な子」「話を聞いていない子」などと言うイメージを持たれやすく、行動が激しく目立つために注意されやすい対象であるとも言えます。
いかがでしたでしょうか?
ADHDという特性を持つ子どもたちは「何がだめなのか」「なんでできないのか」「できない時にどうしたらいいのか」がわからないまま怒られていることがあります。
そして、幼児期に理由はわからないけど「怒られた」という経験が積み重なることで、被害者意識が高まっていくことがあります。
ですので、本人が困っていそうな時、お子さんを育てているご家族が困っている時は、ぜひ子どもがネガティブな経験を積み重ねる前に支援につながっていただけたらと思います。